手帳を拾ってから十日余りの日が過ぎ去っても、持ち主は見つからなかった。商店街一のプレイボーイを自認するオスカーは、この界隈の女性について精通しているつもりだったが、今回ばかりは女性との交際で培った情報網も役には立たない。手帳をなくした女性が数人いはしたが、誰もが自分のものではないと言う。困りきったオスカーは、彼の経営する喫茶店の他の、大勢の女性が通う店の店主から情報を引き出すことに決めた。商店街の殆どの店が定休日になっている火の曜日、彼はランジェリーショップを営むリュミエールと、アクセサリーショップの経営者であるオリヴィエを昼食に招いた。
「実はな、この手帳を落として困っているレディを捜しているんだ。お前たち、心当たりはないか」
「私は……存じませんね。筆跡からはずいぶんと若い方のように思われますが」
リュミエールの言葉にオスカーが答えた。
「ああ、俺も最初はそう思って、スモルニィ女学院のお嬢ちゃんたちに尋ねたんだがな、彼女たちが持つには大人っぽすぎるらしいんだ。顔見知りの大学生やOLに尋ねても心当たりがないと言うし、この俺がお手上げ状態だ。ま、苦労する分だけ持ち主に巡り会った時の喜びは大きくなるんだがな」
「あなたらしいですね。私のお店のお客様にも尋ねてみましょう。もしかしたら手がかりが見つかるかもしれません」
オスカーとリュミエールが手帳の持ち主について交わしている会話を黙って聞いていたオリヴィエは、ずっと下を向いたまま声を殺して笑っていたが、彼らの話が一段落したのを見計らって口を開いた。よほど二人の話がおかしかったのか、目尻には涙が浮かんでいる。
「あー、オカシイ。オスカー、アンタってばこの商店街に店を構えてるクセに、この手帳の持ち主も知らないの」
「笑ってるだけなら帰れ、極楽鳥。可憐なレディが困ってるのが、そんなにおもしろいのか」
「おもしろいねぇ」
ムッとしたオスカーに、ニヤニヤと笑いながら答えるオリヴィエに、オスカーが言った。
「何か知ってるな」
「知ってるヨン、その手帳の持ち主でしょ?」
「誰だ?」
「ナ・イ・ショ。明日、本人に取りに来るように伝えといてア・ゲ・ル」
「本当だな?」
「オリヴィエ様を信用しなさいって。店が終わってから来るように言っとくからサ、楽しみにしときないよ。ランチごちそうさま。美味しかったヨ」
鼻歌を歌いながら店を出るオリヴィエを見送ったオスカーは、優雅に食後のハーブティーを飲んでいるリュミエールに言った。
「アイツ、信用できるのか?」
「さあ、私には……」
水の曜日、閉店の看板を出してから30分ほど経った頃、オスカーの店に来客があった。
「こんばんわ!!オスカーさん。俺の手帳を拾ってくれていたんですって?」
可憐な美女を待ちわびていたオスカーは扉を開けて入ってきた人物を見て驚いた。扉の所には自然食品と健康器具の店を出しているランディが息を切らしている。
「ボウヤ、来る所を間違ってやしないか?」
「え?オリヴィエさんが俺の手帳をオスカーさんが持ってくれてるって……。あ、それです、おれの手帳」
テーブルの上を見たランディが手帳を手に取ろうとするのを、オスカーが憮然として遮った。
「この革細工は女性用にしか見えんぞ。なのに自分のだって言い張るのか?」
「外国に行った母さんが、趣味で革細工をしてたんですよ。それで俺にも作ってくれたんです。女の人向けの柄だけど、シンプルだから俺にも使えるって」
「じゃぁ聞くが、この栞は何だ。男がわざわざ白い花を押し花にするなんて、俺は聞いたことがないぞ」
「それは……花屋のマルセルにもらったんです。いい匂いだからって……。せっかくもらったから使ってるんですけど、それが何か?」
オスカーは軽い頭痛を覚えたが、質問を続けた。
「そのシールは何だ?女子高生の間で流行っているヤツじゃないか」
「これはオモチャ屋のゼフェルがくれたんです。店に置いてたけど、日焼けして売り物にできないからって。かわいいから、いっぱい貼っちゃったんですけど、いけませんか?」
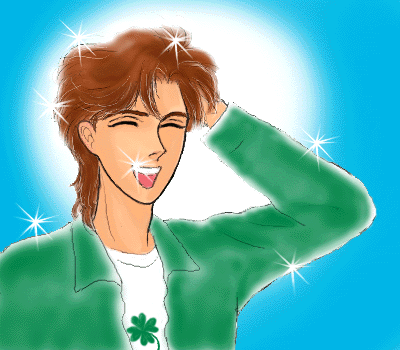
明るく爽やかなランディの笑顔は、可憐な少女像を抱いていたオスカーにとって、もはや凶器でしかない。彼は無意識に芽生えた限りなく殺意に似た黒い感情を抑えるのに懸命だった。それに気づかず、ランディは脳天気としか言えない笑顔で感謝の言葉を口にする。
「俺、バカだから予定をすぐに忘れちゃうんですよ。だから手帳を肌身離さず持っているんですよね。手帳に予定を書いても忘れることが多いんで、友達のゼフェルやマルセルにサインしてもらってるんです。緑色がマルセルで、赤やピンクがゼフェルなんです。予定を書き込む時にどちらかに立ち会ってもらって、サインしてもらって、どんな予定だったかわからなくなったらサインしてくれたほうに聞くんですよ。そしたら、絶対に忘れたり間違ったりしないと思って……」
不自然なほど長く続く沈黙を不振に思ったランディは、オスカーを見た。彼の顔は怒りで紅潮し、その額には怒りの交差点が浮かんでいる。危険な兆候を察してひるんだランディに、オスカーが低い低い声で言った。
「ボウヤ、その手帳に今すぐこの場で、自分の名前を書くんだ。いや、持ち主が見つかった記念に、炎のオスカー様が書いてやろう。感謝しろよ」
オスカーは素早くランディの手の中の手帳を奪い、レジの前に置いてあったペン立ての中から極太の油性マジックで、黒いインクも鮮やかに『ランディ』という4つの文字を、手帳の表紙と裏表紙に書きなぐった。アッという間の出来事に呆然としていたランディだったが、表紙に書かれた自分の名前を見て
「ありがとうございます。これで、次に落としてもすぐに見つかりますね」
と爽やかに言った。
どこまでも素直で、無駄なほどに明るくて、どんな状況でも爽やかなランディは、この瞬間に、商店街一の伊達男・オスカーの不倶戴天の敵となったのである
多少は考えているところもあるはずです……多分。